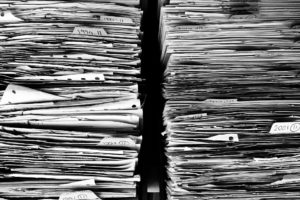金儲けは悪いことか。
私たちは金儲けや金持ちに対して無意識のうちに嫌悪感を抱く。人はなぜ金持ちを嫌うのか、なぜ金儲けを卑しいことと感じてしまうのか。資本主義経済における金を持つことの意味、金を使うことの意味について考察する。
「1のネタ」で働かずして金を稼ぐ方法として「会社の創業者になる」と「投資家になる」という2つの方法を紹介した。
ここではこの2つの方法について今後詳細に話していく。
その前にまず「金儲けは悪いことか」ということについて、考えていきたい。
金持ちに対する無意識に抱く悪いイメージの正体
多くの人は「金儲けは悪いこと」であると考えている。「金持ち」をイメージしてくださいと言われると、太った男が両脇にけばけばしい女性を抱きながら葉巻を吸っているイメージや、金ぴかな宝飾品で全身を固めたがめつそうな女性の姿などを想像するのではないか。
「金儲け」と聞くと、何か悪いこと、人をだましてお金を奪うことなどを連想する人も多いかもしれない。
逆に「働く」と聞くと、汗水垂らして努力する姿、みんなで団結して協力する姿などが頭に浮かばないだろうか。
これら社会が植え付けたイメージは強烈であり、また想像以上に深く人々の間に根付いている。「金儲け」、特に「労働を伴わない(働かない)金儲け」はさも「悪いこと」であり、「楽な方法」であり、「下品で下衆で、醜く、恥ずべき行為」なように捉えられることが非常に多いように思われる。
このようなイメージは突き詰めていくと金持ちへの妬みなのではないかと考える。自分はこんなに頑張って働いているのに、あいつはろくに努力もしないで自分以上に稼いでいる、大金を稼いで私利私欲のためだけに使っている、など、自分にできないことをできる人間に対する妬みが深層心理にあるのではないか。そしてこのような「働かない金儲け」を悪として敵視することで自分の心の平静を保っているのではないか。
金持ちが金を使うことで経済は回る
犯罪行為でない限り、稼いだ金で私利私欲を満たすのは別に構わないと思う部分もあるが、それでもそのような行為が人々に嫌悪感を抱かせ、「金を稼ぐこと」の地位を貶めているように思う。
しかし、彼らが私利私欲を満たす、つまり商品やサービスを消費することで、社会・経済は回っている。彼らが金を使うことでその金は商品・サービスの提供者へと渡り、そこの労働者に給料が支払われ、その給料を使って別の商品・サービスを消費することでまた別の労働者へとお金は移り、・・・このようにして社会は成り立っている。金持ちが金を使わないでため込んでいたら、その金は誰の手にも渡らず、消費がされず、商品・サービスの提供者は収入が減り、労働者の給料は減り、社会全体が困窮していく。
また別のことも考えてほしい。世界の大金持ちたちは驚くほど膨大な金を寄付や慈善事業に使っている。節税のために寄付などをしていると一蹴することもできるが、用途不明な税金として徴収する場合としっかりと目的をもった寄付や慈善事業に金が渡る場合、どちらのほうが社会貢献・社会厚生に寄与するだろうか。
金儲けは悪いことか
金を稼ぐのは悪いことではない。働かないで稼げるならそれに越したことはない。嫌悪すべきは「金を稼ぐこと」ではない。「金の使い方」が重要なのではないか。